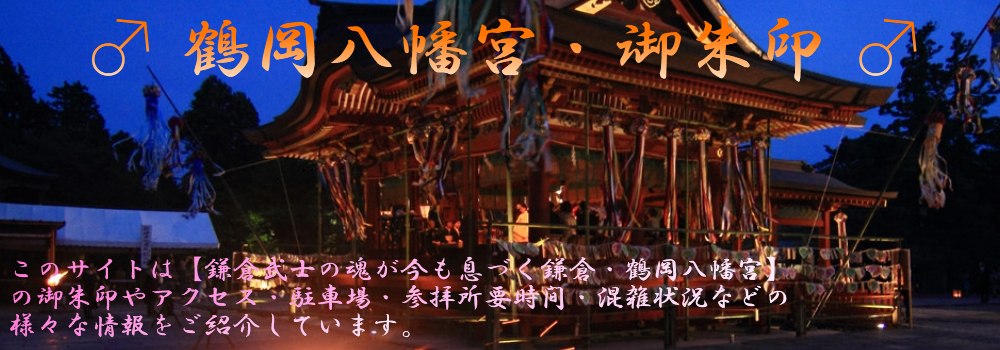鎌倉・寿福寺
読み方:じゅふくじ
正式名:亀谷山 壽福金剛禅寺
※寿福寺の「寿福」は「壽福」と書くのが正式。
宗派:臨済宗 建長寺派
創建年:1200年(正治二年)
開基:北条政子
開山:明庵栄西(みょうあん えいさい/ようさい)※「葉上房 栄西(ようじょうぼう)」とも
本願主:土屋次郎義清
寺格:鎌倉五山・第三位
国指定史跡指定年月日:1966年(昭和41年)3月22日
※2008年(平成20年)7月28日には石切山(境内後方)のやぐら群、切岸など追加指定。
寿福寺の歴史
1180年(治承四年)10月6日、源頼朝卿は房総半島(安房国)から下総、武蔵国、そして鎌倉へと至り、その翌日(7日)、自らの館となる場所を求めて現在の寿福寺が建つ、亀ヶ谷の地を巡検する。
何と言っても、この亀ヶ谷の地には頼朝卿の父・源義朝の亀谷館が建っていた源氏ゆかりの地でもあり、頼朝卿は鎌倉入部が決まった後より当地に居館を建てることを心に決めていた。
しクぁし!
以下の理由で頼朝卿は亀ヶ谷に自邸を構えることは見送った。
頼朝卿は「この地は谷戸が複雑に入りんだ地形をしていて、広さを求められない」とし、近臣の岡崎平四郎義実は「父・義朝公の没後、その菩提を弔うべく、一の梵宇(法華堂)を建てた場所」などと進言したことにも拠る。
確かに頼朝卿からすれば、父・義朝の近臣でもあった岡崎平四郎義実(三浦義明の弟)が義朝の菩提を弔うべく建てた御堂を移動させてまでして、どぅしてその場所に自邸を建てることなどできよぅか?‥‥というものだったのだろぅ。
寿福寺の創建理由
1199年(建久十年)1月13日、源氏の英雄・源頼朝卿が永眠の常楽に至ると、その翌1200年閏2月12日、その妻である北条政子は頼朝卿の菩提を弔う意味合いも込め、義朝公から相伝される亀谷の地(現在の寿福寺の場所)を栄西に寄進する。
そして、栄西禅師を開山に据え、自らが開基となって寿福寺建立を発願した。
これは自身の亀谷館の建設を生前、見送った頼朝卿の意思を叶える事でもあった。
寿福寺建立計画
政子によって寿福寺建立計画が立案されると、当地の巡検のために直ちに二階堂行光、三善善信が遣わされた。
両名はまず、寺域の前方を南北する武蔵大路とし、東方へ向かえば武蔵国六浦荘(むつらのしょう/横浜市金沢区)に通じる立地と定めた。
ただ、当地は義朝の旧跡でありつつも、岡崎義実の次男坊たる土屋次郎義清が管理を任された亀谷堂の地でもあったが、いずれせよ翌日(1200年閏2月13日)には「清浄結界の地たるべし」と下知され、栄西禅師に寄進された。
寿福寺の完成日(造営期間)は謎💋
1200年(正治二年)閏2月13日の午の刻(12時)、北条政子を施主とし、寿福寺造営の事始め(儀式)が執行されたが、完工がいつ頃なのかは判然とせず、現在に至っても未詳とされる。
しクぁしながら、吾妻鏡によると1202年(建仁二年)当時、沼浜(逗子市 沼間)に在った義朝の旧宅を解体して、その廃材を亀谷寺(寿福寺)の建設に使用された旨の記述がみえることから、少なく見積もっても1202年以降に完成を迎えたことになる。
正治二年(1200年)7月15日が寿福寺の完工とする見解もある
寿福寺建立計画直後の1200年(正治二年)7月6日、政子が京都に依頼した「十六羅漢図」が完成し、在京御家人の佐々木定綱がそれを鎌倉へ届けた。
政子はその十六羅漢図を「葉上坊(栄西)の寺」に造進し、同15日以降になると十六羅漢図の開眼供養が「金剛寿福寺」で執行された事が吾妻鏡には記される。
ここで注目すべきは寿福寺の表記が「葉上坊(栄西)の寺」から→「金剛寿福寺」へ変わっていることにあるが、これはある程度、寿福寺造営計画が成った経過を意味し、すなわち、1200年(正治二年)7月15日に寿福寺が建立された日とする見解もある。
ただ、もし完工が正治二年(1200年)7月15日とすると、着工から半年も経たずに落慶したことになるが、これはどうみてもおかしい。
計画された寿福寺は大規模とはいえないものがあったようだが、七堂(金堂(本堂)・講堂・塔・鐘楼・経蔵・僧房・食堂)を備えた伽藍だったとする説もあり、いずれにせよ工期が半年というのは建材調達期間を加味しても早すぎる。
‥‥ということで正治二年(1200年)7月15日には、まだ寿福寺が完成していなかったと見る説が濃厚とみる。
寿福寺の建材の調達場所
ところで寿福寺造営に際して鎌倉の地形柄、建材の確保にも一苦労あったようだが、これに関しては前述、義朝の旧宅のほか、大倉御所の侍所を再建した際に生じた廃材を使用したとも伝わる。
大倉御所の侍所は1212年(建暦二年)6月7日の丑の刻(午前2時)、当時、宿直をしていた御家人が乱闘騒ぎを起こして刀傷が諸所に付いたことから千葉介成胤が造進(再建)する運びとなったことが鏡に記される。
政子の夢枕に立った義朝の亡霊が寿福寺創建を打診?
正治二年(1200年)の”とある夜”、政子の夢枕に義朝が立ち、こぅ告げたそぅな。
『吾れ、つねに沼浜の亭に在り。しかるに海浜では漁をきわむ(漁=殺生)。吾れが亭を壊ちて寿福寺内に移建せしめ、吾れは六楽を得んと欲す』
これを訳すと、義朝は当地(寿福寺の場所)にて供養されたものの自らの魂は沼浜の自邸に留まり、漁をして海の幸を食べている(=殺生)ので、自邸を壊してソッチ(寿福寺内)へ移りたい。そぅすれば極楽往生できる。‥‥‥などの意味になると思われる。
‥‥と、以上のような夢を見た事で政子は義朝の沼浜の亭の取り壊しを決意し、その廃材を寿福寺造営の用材としたのかも知れなぅぃ。
栄西は源頼家建立の建仁寺の開山でもある
1202年(建仁2年)、鎌倉幕府2代目将軍・源頼家は中央(京都)において臨済禅を広めることを目的とし、元号を寺号として「京都・建仁寺」を創建し、開山を栄西に据えた。
この当時、栄西は京都と鎌倉を往来する忙しい日々を送っていたと云われる。
栄西について
栄西は鎌倉幕府に最初に帰依を受けた禅僧となるも、この当時、台密(たいみつ/最澄開創の天台密教)の権威としても知られており、幕府における仏事などに導師として招聘された際も度々、台密の密教式行法を用いたのだった。
それゆえ、当初の寿福寺は純粋な禅宗寺院とはいえず、厳密には天台宗との兼宗兼学の寺院だった。
伽藍の規模はけっして大きいとはいえないものがあったが、それでも栄西という人物を慕ぅぃ多くの門弟が宗門を叩くなど、退耕行勇はじめ、日本初の「聖一国師」たる円爾(えんに/弁円とも)など、歴史上に名を残す人物を輩出した。
あまり知られていない!蘭渓道隆は寿福寺の住職だった!
栄西や行勇が他界した後も「栄西の寿福寺」として相伝され、1248年(宝治二年)に鎌倉入りを果たした名僧・蘭渓道隆(らんけいどうりゅう)も、まず最初にこの寿福寺へ来山したと伝わる。
蘭渓道隆は第5代執権の北条時頼より帰依を受け、粟船(あわふね)常楽寺の開山となったが、道隆はその後、第五世住職としてこの寿福寺へ入寺した話はあまり知られていない。
実朝も頻繁に訪れた寿福寺
鎌倉幕府3代目将軍・源実朝は栄西禅師に深く帰依し、幕府の法要の導師を栄西に請いたり、はたまた自身も、たびたび寿福寺へ足を運んで栄西と談笑を交えながら、よく教えを学びんだと伝わる。
実朝がこの後、渡宋計画を立てて大船を建造したのも、この栄西の影響に拠るところが大きい。
土屋次郎義清が寿福寺に埋葬される
1213年(建保元年)5月3日、和田方の将として和田合戦に参戦した土屋次郎義清が敗死すると、その亡骸は寿福寺に埋葬される運びとなった。
これは土屋次郎義清が、父・岡崎義実や源義朝公から相伝される当地の管理者(持ち主)だったからであり、寿福寺造営に際し当地を譲った本願主だったことにも因む。(土屋次郎義清は当地を譲った後、一等地ともなる若宮大路通り西側、和田義盛宅の隣地に屋地を与えられてい申す)
同年12月3日には栄西禅師を導師に招聘し、和田合戦の戦没者供養の仏事が寿福寺で執行された。
栄西の死、退耕行勇が寿福寺長老に就任す
吾妻鏡によると1215年(建保三年)6月5日、栄西は寿福寺で遷化したと記す。(「元亨釈書」「沙石集」には建保三年7月5日に建仁寺で死没したと記す)
そして、翌1216年(建保四年)5月12日、師である栄西の意志を継承し、その弟子たる退耕行勇が寿福寺長老に就任する。
実朝はこの退耕行勇にも深く帰依しており、5月25日、自らが年来大切に所持していた牛王(ごおう/熊野護符)を退耕行勇に下賜してい‥‥‥申す。ぎゅぉっ..あ、”ごおっ”やった
寿福寺を襲った火災
鎌倉市中では度々、火災が発生したが、ついにその牙がこの寿福寺へも向く。
1247年(宝治元年)11月7日の丑の刻(午前2時)、寿福寺境内の失火にて仏殿以下、惣門(入口の山門)に至るまで悉く焼亡に至る。
なお、この再建がいつ頃に成されたのは未詳とされるも、わりと早期に再建されたとする説もある。
翌、建長四年には寿福寺のすぐ前で大火事があり、南は和賀江島手前、北は若宮大路の丘上、東は名越までの広範囲に渡って全焼してい‥‥申す。ゲハっ
1258年(正嘉二年)の火災で再び寿福寺境内が全焼す!
1258年(正嘉二年)正月17日の丑の刻(午前二時)、安達泰盛の甘縄亭から失火が起こる。
甘縄は由比ヶ浜や長谷にほど近い、鎌倉南端にも関わらず北風に煽られたせいもあってか、鎌倉市中を越えて寿福寺境内をも飲み込み、惣門、仏殿、庫裡、方丈以下、境内一宇も残さずに灰燼に帰したことが記される。(安達泰盛邸の場所は扇ヶ谷という説もある)
この火事は鎌倉時代の数ある火事の中でも大規模火災として知られ、鶴岡若宮なども全焼に至ってい‥‥‥申す。ごぉ(火事を簡素に表現)
大休正念が第六世住持として入山す
第五世住持の蘭渓道隆の意志を継承したのが、1269年(文永六年)に8代目執権・北条時宗の招聘によって南宋より来朝した大休正念(だいきゅうしょうねん)だった。
正念は建長寺三世住持、浄智寺の開山としても知られているが、後にこの寿福寺へも第六世住持として入寺してい‥‥‥申す。あひょ
1283年(弘安六年)には自身の寿塔(生前建立の墓)として塔頭(たっちゅう)の蔵六庵を開創す。
なぜ「蔵六」なのか?「仏教の教え」
仏教には次のような教えがある。
『我欲を謹むをいう。祖底事苑に、雑阿合経に、亀あり、野干(きつね)に捕えられる。
亀は六を蔵(かく)して出さず。
野干怒って捨て去る。
仏(釈迦)諸の比丘に告げて曰く。
汝等当(まさ)に亀の六を蔵するが如くすべし。
自ら六根(眼耳鼻舌身意の欲)を蔵せば、魔も便を得ず云々』
亀の蔵六に倣ぃ、自らの蔵六となる六根(眼耳鼻舌身意の欲)を隠せば、災いが生じることもない。‥‥などの意。
なお、蔵六庵は1335年(建武二年)に円覚寺境内に移建され、以後は円覚寺塔頭として現存す。
1311年に鎌倉五山第3位に列せられる!
1311年(応長元年頃)、寿福寺は建長寺・円覚寺の両寺とともに五山に列せられるに至る。(建長寺は第1位、円覚寺は第2位)
北条貞時十三年忌供養が盛大に厳修される
1323年(元亨三年)10月、第9代執権・北条貞時の十三年忌供養が寿福寺で執行される運びとなり、その参加者も長老以下、一山の僧衆含め260人にものぼった事が鏡に記される。
この人数は建長寺・円覚寺に次ぐものであり、同時に鎌倉五山・第三位たる寿福寺の寺格を示すバロメーターともなる。
ちなみに、このすぐ後に鎌倉五山第4位の浄智寺の224人が続く。
寿福寺の衰微
寿福寺は1476年(応仁元年)にも火難に見舞われたが、この再建計画は大幅に遅延が生じた。
大きな理由は当時の鎌倉の権力者だった鎌倉公方たる足利成氏(あしかが しげうじ/初代・古河公方)が、享徳の乱の最中となる1455年(享徳四年)に鎌倉を放棄し、下総・古河へ移ったことが挙げられる。
星霜経て、開山五百年忌が執行された1714年(正徳四年/江戸時代中期)に寿福寺再建計画が成ると、まず仏殿が再興され、1751年〜1764年(宝暦年間)の間に一応の寺観が復興をみた。
1771年(明和八年)には梵鐘の鋳造が行われるなど、以後、江戸末期にかけてほぼ、現在見られるような寺観が整った。
言うならば、1476年(室町時代)よりの約300年間は更地に近い状態で荒廃していた事になり、これは当時の鎌倉の情勢(有り様)を投影したものとみる事もできる。
1633年に沢庵宗彭が来山す
1633年(寛永十年)、臨済宗の大僧にして大徳寺(京都)住持の沢庵宗彭(たくあん そうほう)が寿福寺へ来山する。
しクぁし!
沢庵宗彭曰く、「仏殿も かたばかり(形の無い口伝だけの)の体(てい)なり」‥‥と、栄西の塔所となる逍遥院すらも失われた当時の寿福寺の惨状を悲嘆したことが旧記に記される。
鎌倉幕府が滅び、長らくの戦乱の時を経て、よぅやく家康公によって天下が鎮まった間も無くの頃、「栄西の寿福寺」と謳われたかつての寺院の姿はすでにそこにはなく、辛うじて残された一院に栄西(千光国師)の尊像を奉安し、香灯を手向けるという有様だった模様。
昭和時代には近代詩人の中原中也が寿福寺境内で暮らした
1937年(昭和12年)2月、東京を離れた病み上がりの中原中也(なかはらちゅうや/詩人)は鎌倉町扇ヶ谷の寿福寺境内にあった借家へと転居し、5月に新作となる「春日狂想」を発表してい‥‥申す。きゃ
実朝公に関連した寺院は「金剛」と名付く例が多ぃ
考えてみると、この寿福寺(金剛禅寺)はじめ、金剛三昧院(高野山)、金剛寺(現・東京都中野区上高田)など実朝公を奉斎した寺院は「金剛」の文字を冠した例が多いが‥‥‥はてさて。
寿福寺の歴史(年表)
鎌倉時代
| 年 | できごと |
| 1180年(治承四年)10月6日 | 頼朝卿が寿福寺が建つ亀谷(亀ヶ谷)の地を巡検する |
| 1199年(承久十年)正月13日 | 頼朝卿、死没す。 |
| 1200年(正治二年)閏2月12日 | 北条政子が寿福寺建立計画を掲げる。 |
| 同7月15日 | 寿福寺にて十六羅漢図の開眼供養が厳修される。 |
| 1204年(元久元年)5月16日 | 政子が祖父母の追善を寿福寺にて執行す。 |
| 1213年(建保元年)5月3日 | 寿福寺の本願主でもあった鎌倉幕府御家人の土屋次郎義清の亡骸が寿福寺へ埋葬される。 |
| 1214年(建保二年)2月 | 宿酔で苦しむ実朝に栄西が茶を進めた折、「喫茶養生記」を手渡す。 |
| 1215年(建保三年) | 栄西禅師が寿福寺にて示寂す。(諸説あり) |
| 1216年(建保四年)4月8日 | 実朝が寿福寺へ参拝す。 |
| 同7月15日 | 北条政子が参拝す。 |
| 1217年(建保五年)5月12日 | 退耕行勇が寿福寺長老に就任す。 |
| 年 | できごと |
| 同5月15日 | 実朝が北条泰時・時房を随伴し来山す。 |
| 同5月29日 | 北条政子が来山す。 |
| 1247年(宝治元年)11月7日 (丑の刻/午前2時) |
寿福寺境内の失火にて境内全焼す。 |
| 1248年(宝治二年) | 蘭渓道隆が寿福寺へ来山し、後、住職となる。 |
| 1258年(正嘉二年)正月17日 (丑の刻/午前2時) |
鎌倉幕府・御家人の安達泰盛宅の甘縄宅からの失火にて、寿福寺境内が再び灰燼に帰す。 |
| 1269年(文永六年) | 大休正念が第六世住職として寿福寺へ入山す。 |
| 1283年(弘安六年) | 蘭渓道隆が蔵六庵を造営す。 |
| 1311年(応長元年)頃 | 寿福寺が建長寺・円覚寺に並び鎌倉五山の第三位に列せられる。(建長寺が1位、円覚寺が第2位) |
| 1323年(元亨三年)10月 | 鎌倉幕府9代目執権・北条貞時の十三年忌供養が寿福寺で執行される。 |
室町時代
| 1335年(建武二年) | 蔵六庵が円覚寺へ移築される。 |
| 1358年(延文三年)9月2日 | 吾妻鏡に寿福寺が鎌倉五山の第3位である事実が記される。 |
| 1362年(慶安二年) | 伽藍神倚像(市文)が奉安される。 |
| 1395年(応永二年) | 火災により炎上す。 |
| 1467年(応仁元年) | 寿福寺が火難に見舞われる。 |
| 1714年(正徳四年) | 開山五百年忌にて仏殿が再興される。 |
| 1771年(明和八年) | 梵鐘の鋳造成る。 |
| 1633年(寛永十年) | 沢庵宗彭が来山し、栄西禅師の尊像を納置し、菩提を弔う。 |
昭和時代
| 年 | できごと |
| 1937年(昭和十二年)2月 | 中原中也が寿福寺境内に住む。同年5月、「春日狂想」を発表す。 |
昭和時代
| 年 | できごと |
| 1966年(昭和41年)3月22日 | 国指定史跡の指定を受ける。 |
平成時代
| 年 | できごと |
| 2008年(平成20年)7月28日 | 石切山(境内後方)のやぐら群、切岸などが国指定史跡の追加指定を受ける。 |
寿福寺に奉安された仏像や宝物など
- 木造・宝冠釈迦三尊像(本尊)※脇侍に文殊&普賢坐像をいただく
- 達磨大師像
- 仁王像(元・鶴岡八幡宮寺の仁王門安置)
- 伽藍神倚像(がらんじんいぞう/鎌倉市重文指定)
- 木造地蔵菩薩像(重文指定)
- 栄西禅師像(県重文指定)
- 銅造 薬師如来坐像(鎌倉前期造立/神仏分離の折、鶴岡八幡宮寺から寿福寺へ移された尊像)
- 栄西禅師筆の喫茶養生記(きっさようじょうき/重文指定)
概要
釈迦三尊像および脇侍2躯含む
- 文化財指定日:1982年(昭和57年)2月9日
- 造立年:室町時代
- 造立方法:中尊は脱活乾漆造、脇侍は寄木造
- 像高(中尊の釈迦如来像):2.95m
木造栄西禅師像
- 文化財指定日:1954年(昭和29年)3月30日(現在、鎌倉国宝館に寄託)
- 造立年:鎌倉時代
- 造立方法:一木割矧ぎ造
- 像高:60.4cm
木造達磨大師坐像
- 文化財指定日:1981年(昭和56年)7月17日
- 造立年:室町時代(南北朝時代)
- 造立方法:寄木造
本尊・釈迦三尊像の釈迦像は別名「籠釈迦」とも呼ばれる
寿福寺本尊の釈迦三尊像(原則一般非公開)の釈迦像は別名「籠釈迦」とも呼ばれるが、これは籠に布や紙などを張り合わせて作られた脱活乾漆造の尊像となるため、この名前が古今、相伝される。像高2.95m。
また、その胎内には実朝or政子が数百枚にわたって描いたと伝わる「白衣観音画像」が納置されるが、現在は100枚もなぅぃ。
脱活乾漆造は、奈良時代に多用された造立方法であり、東大寺・不空羂索観音菩薩立像など、僅かな類例しかなく貴重とされる。
寿福寺境内の有名人の墓など
陸奥宗光、陸奥広吉、高島直一郎(高島小金治の長男)、山田忠澄、高浜虚子、星野立子(高浜虚子の次女※句碑あり)、大仏次郎、田邊新之助、中原中也(現代文学者)….etc
寿福寺仏殿のビャクシン(柏槇)
一般公開されていないので知らない方がほとんどだが、寿福寺仏殿前の前庭には4株のビャクシン(柏槇)が自生する。
このビャクシンは現今、鎌倉市指定天然記念物の指定を受けるも、老木が見せるその姿は往時の宋風禅寺であった寿福寺の威容を偲ばせる。
 ⬆️僕が君のために虹を捕まえてやる!‥‥と言って本当に虹が捕まえれた時のア然具合ほど噂の‥‥「寿福寺仏殿前前庭」…ビャクシンある?
⬆️僕が君のために虹を捕まえてやる!‥‥と言って本当に虹が捕まえれた時のア然具合ほど噂の‥‥「寿福寺仏殿前前庭」…ビャクシンある?
ちなみにビャクシンとはこぅ言う樹木!
 画像はウィキより
画像はウィキより
寿福寺の場所(地図)
- 所在地:鎌倉氏扇ヶ谷1丁目17-1
- 鎌倉駅から北へ徒歩約10分
- 鶴岡八幡宮から西へ徒歩約5分
関連記事一覧
関連記事:![]() 【寿福寺裏山】源実朝の墓と北条政子の墓の場所と行き方を….ラジオ体操しつつ知りたいと願ったね❓
【寿福寺裏山】源実朝の墓と北条政子の墓の場所と行き方を….ラジオ体操しつつ知りたいと願ったね❓
関連記事:![]() 【寿福寺裏山の北条政子の墓】歴史や造りを….コチョバされながら知るつもりぃ❓|鎌倉市 扇ケ谷
【寿福寺裏山の北条政子の墓】歴史や造りを….コチョバされながら知るつもりぃ❓|鎌倉市 扇ケ谷
スポンサードリンク -Sponsored Link-
当サイトの内容には一部、専門性のある掲載がありますが、これらは信頼できる情報源を複数参照して掲載しているつもりです。 また、閲覧者様に予告なく内容を変更することがありますのでご了承下さい。