鎌倉 長谷寺の歴史(年表)
奈良時代
| 年 | できごと |
| 721年(養老五年) | 大和(奈良)の僧・徳道が、1本の大楠から2体の十一面観音を彫る。 そのうち1体は奈良県桜井市に長谷寺を開き、本尊として安置。 もう1体を海に流したと伝えられる |
| 736年(天平八年) | 相模の三浦半島に流された十一面観音が流れ着く。 藤原房前が大和から徳道を呼び寄せ、この十一面観音像を本尊として、鎌倉長谷寺を開山 |
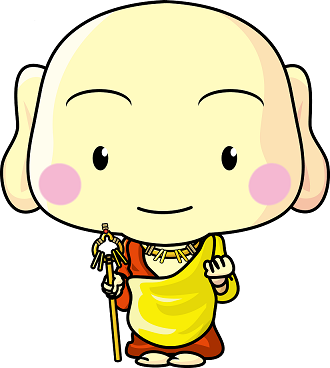
💋長谷寺を建てた人💋
- 開山:徳道
- 開基:藤原房前(藤原不比等を父とする藤原四兄弟の次男で藤原北家の祖)
最初に言っておくと長谷寺の歴史は途切れ途切れの断片的に文献などの歴史に登場するのみなんだ。だから謎多きお寺なんだよ♪
僕も「謎多きキャラだね」ってよく言われるけど、実は僕のこの格好コスプレなんだ。昨日、脱衣野球拳で大負けブッこいて、逆にこんなお坊さんのコスプレ着さされたんだ。
僕も早く立ち直りたぃから、とりえず長谷寺の歴史についてクっちゃべって気を紛らわせておくことにするよ。
鎌倉時代
| 年 | できごと |
| 1200年(正治二年) | 鎌倉幕府・公文所の別当「大江広元(おおえのひろもと)」が長谷寺を再建す。 |
| 1243年(仁治四年) | 銅造 鍍金経筒が制作される。 |
| 1247年〜1248年(宝治年間) | 建長寺(鎌倉五山一位)が長谷寺建立に関与している事実が発覚す。創建当初の長谷寺は真言律宗とも。 |
| 1262年(弘長二年) | 【鎌倉市指定文化財】阿弥陀如来種子(梵字)板碑造立される |
| 1264年(文永元年) | 新長谷寺の梵鐘(重文指定)が鋳造される。 「真光(当時の住職)勧進」「鋳物師物部季重 造立」などの銘文があり、 これがまず文永元年にはすでに存在していたことが明らかになる。 また、この当時の長谷寺は「新長谷寺」と称していたことも明らかにされている。 しかしそれ以前の記録はなく、奈良時代の開山については伝承の域を出ない。鎌倉幕府7代将軍「惟康親王」が本堂(観音堂)を建立す。 亀山院より寺号額(「長谷寺」)を下賜される。 長谷寺の調査によると勅願所に定められたのも、この頃という説を素敵に述べる。 |
| 1308年(徳治三年) | 宝篋印塔の陽刻板碑が制作される。 (現、鎌倉市指定文化財) |
| 1330年(元徳二年) | 銅造十一面観音像懸け仏 (かけぼとけ/国重文指定※銅鏡面に仏像を取り付けたもの)が鋳造される |
室町時代
| 年 | できごと |
| 1342年(康永元年) | 足利尊氏が観音堂を再建す。 相模国 高座郡 座間村(現・神奈川県座間市)の土地を 燈明領として寄進す。 また本尊・十一面観音像を修復し、金箔を施す。 |
| 1392年(明徳三年) | 三代将軍・足利義満によって十一面観音像の光背が修復される。 さらに行基作と伝えられている前立観音が安置される。 |
| 1412年(応永十九年) | 木造 阿弥陀如来坐像(阿弥陀堂本尊の丈六仏)が再興される。 木造 大黒天像が造立される(県内最古) |
| 1413年(応永二十年) | 銅造の鰐口が制作される(神奈川県指定文化財) |
| 1450年(宝徳二年) | 8代将軍・足利義政が観音堂を再建す。 前立ち観音、三十三応現身像を修復す。 |
| 1476年(文明八年) | 木造 三十三応現身像(鎌倉市指定文化財)の内、 一躯の修復が完了す。 |
| 1480年(文明十二年) | 後土御門院より「祈祷」額を下賜される。 |
| 1485年(文明十七年) | 十一面観音像の木造雲形光背の一部の修復が成る。 |
| 1490年(延徳二年) | 足利義政が没し、 その法名により長谷寺に「慈照院」の院号が下賜される。 当寺の見解では、 これが別当・慈照院創建の由来とする説がある。 |
| 1533年(天文二年) | 寺伝によると上杉長谷御前が観音堂を修復し、 前立ち観音像および三十三応現身像に彩色を施したと伝わる。 |
| 年 | できごと |
| 1543年(天文十二年) | 仏師・泉円により三十三応現身像の一部が修復される。 |
| 1547年(天文十六年) | 北条氏康(相模国・後北条氏第3代目当主)が 長谷寺の寄進地2貫文を安堵す。 |
| 1557年(弘治三年) | 長谷寺縁起絵巻が制作される(神奈川県指定文化財) |
| 1590年(天正十八年) | 太閤秀吉が長谷寺に禁制を下す。 |
| 1591年(天正十九年) | 徳川家康公より灯明料2貫文の寄進を受ける。 太閤秀吉による小田原征伐成功の褒賞として 三河(愛知県)から→かつて北条氏が支配した関東一帯が 徳川家康公の所領として割り当てられる。 その家康公から長谷寺の所領は 以前のまま朱印料として安堵される。 |
| 1593年(文禄二年) | 光明寺所蔵の文書によると、 この頃、慈眼庵が称号を改め慈眼院とす。 |
| 1600年(慶長五年) | 徳川家康公が長谷寺へ参拝す。 |
江戸時代
| 年 | できごと |
| 1607年 (慶長十二年) |
徳川家康によって堂塔伽藍の改修が行われる。 浄土宗へと改宗。 |
| 1617年 (元和三年) |
2代将軍・徳川秀忠公が観音堂の所領として 2貫文の土地を安堵す。 |
| 1632年 (寛永九年) |
浄土宗本末寺院帳の光明寺末として 長谷寺・慈照院・慈眼院が定まる。 |
| 1638年 (寛永十五年) |
丈六・阿弥陀如来像(旧・誓願寺本尊)が 英勝院の協力によって修復される。 |
| 1645年 (正保二年) |
酒井忠勝が本堂を修営す。 住持・玉誉春宗が光明寺の |
| 1648年 (慶安元年) |
舊(旧)應和尚に請い、 長谷寺と光明寺の本末関係が成立す。 |
| 1666年 (寛文六年) |
慈眼院・慈照院の主導による 長谷寺両別当制度が開始される。 |
| 1672年 (寛文十二年) |
丈六 阿弥陀如来坐像が再修理される。 |
| 1674年 (延宝二年) |
木造 善導・法然両祖師像が造立される。(浅草今戸の常照院(現在は廃寺)の旧什物とされる) |
| 年 | できごと |
| 1676年 (延宝四年) |
「長谷寺縁起絵・巻2巻」を長谷寺の什物(什器のこと)として、 住持・法誉弁秋(ほうよべんしゅう)が施入す。 |
| 1677年 (延宝五年) |
光明寺所蔵の文書によると、 この頃、長谷寺境内伽藍の本格的な整備が実施される。 また、長谷寺住持の法誉弁秋の訴状が容認され、 長谷寺は別当であった慈照院による一院管理下に置かれる。 |
| 1680年 (延宝八年) |
法誉弁秋が木造 弥勒菩薩坐像を造立す。 |
| 1682年(天和二年) | 法誉弁秋、相州鎌倉海光山長谷寺事実を編纂す。 |
| 1683年(天和三年) | 武州荏田(現在の神奈川県横浜市青葉区〜都筑区に相当) の不動尊(矢羽根不動尊)が、 弁秋の協力を仰ぎ造立される。 (台座の刻銘によると仏師は長谷寺仏師の菊池加賀守とされる) |
| 1686年(貞享三年) | 慈眼院の不服申し立てにより、慈照院の一院管理から 慈眼・慈照両院による輪番制の管理体制に戻る。 |
| 1687年(貞享四年) | 光明寺の文書によると、法誉弁秋が糾弾され、 長谷寺よりの退去を迫られる。 この頃、前出の浅草常照院の住持・運哲が慈眼院に転住す。 |
| 1691年(元禄四年) | 長谷寺境内なのかは未詳とされるが、この年、長谷寺敷地に阿弥陀堂が建立され、 丈六サイズの木造 阿弥陀像が遷座したとある。 |
| 1694年(元禄七年) | 法誉弁秋が没す。…グハっ |
| 年 | できごと |
| 1697年(元禄十年) | 丈六 阿弥陀如来・勢至菩薩両像の台座が新造される。 |
| 1703年(元禄十六年) | 元禄の大地震によって鎌倉は甚大な被害を被る。 長谷寺境内も罹災す。 |
| 1704年(宝永元年) | 建長寺の文書によると、元禄の大地震によって罹災した新居の閻魔堂(現在の円応寺)が 旧跡地であった大仏近くの奥山(当時は「長谷 見越嶽」と呼ばれた※現・長谷寺境内の奥山)にて再興を求願す。 |
| 1712年(正徳二年) | 鎌倉市史によると、 この頃、長谷寺の所管にあった鎌倉大仏(現・高徳院)が 長谷寺の所管から離れ、光明寺(鎌倉)の末寺として移管されたとある。 |
| 1724年(享保九年) | 瀧山 大善寺の融音が長谷観音の「頂上仏縁起」を編纂す。 |
| 1741年(寛保元年) | 三十三応現身像が修復される。 (のちに台座より江戸仏師・万屋善兵衛の刻銘が見つかる。) |
| 1816年(文化十三年) | 「長谷村浄土宗 長谷寺慈眼院 明細書上」が成立す。 |
| 1866年(慶応二年) | 本山 光明寺より制約が到来す。見越岳(嵩)とも書く。標高約八〇メートル。「攬勝考」は大仏より東の山をいい、大仏を見越すという意味
皇国地誌には長谷村の中央、最高所二〇余丈、山並は東は長楽寺ちようらくじ山に連なり、三方は田圃へ臨み、松杉や雑樹が蕃叢すると伝える。 これは甘縄あまなわ神明社の背後の山(別名神明山)になるが、一般的には、鎌倉大仏の背後の山並が稲村いなむらヶ崎の近くで海岸に接する霊山りようぜんガ崎をさすと考えられている。 |
【ピヨ🐣「長谷 見越嶽(みこしがたけ)」とは?】
「見越嶽」とは、「御輿ヶ嶽」や「見越岳(嵩)」とも書かれるらしく、長谷寺奥の標高約八〇メートルの丘陵のこと。
江戸期に水戸黄門が編纂させた「鎌倉攬勝考(らんしょうこう)」によると、「見越嶽」とは「鎌倉大仏より東の山」を指し、”大仏を見越す”という意味になるらしい。
明治初期編纂の「皇国地誌(こうこくちし)」によると、見越嶽について次のように記す。
『長谷村の中央、最高所二〇余丈、山並、東は長楽寺山に連なり、三方は田圃へ臨み、松杉や雑樹が遮蔽(壁)のように繁茂する』
なお、この文面の指し示す場所は、「甘縄神明社の背後の山(別名・神明山)」にも比定されるのだが、現在までの通説では、鎌倉大仏 背後の山並が、稲村ヶ崎付近で海岸に接合する「霊山ガ崎」を指すと考えられてい‥申す。えっ
【ピヨ🐣「霊山ガ崎(りょうざんがさき)」とは?】
「霊仙山」とも書き、稲村ヶ崎の北東方に連なる標高八三メートル余の丘陵。
丘陵の稜線が南方の海岸に突出したように見える部分は、古名で「霊山ガ崎」とも呼ばれる‥も!現在、湘南有料道路が営まれるなど、”旧観”は”急患”で”休館”になっちまぅほどに失われた。 どんな失くし方や
ともあれ、北の極楽寺に伝蔵される「極楽寺縁起」によると、鎌倉時代後期あたりから、この山の頂には、「仏法寺(ぶっぽう)」という、極楽寺に属する寺院が佇んでいたたらしい。
明治時代
| 年 | できごと |
| 1874年 (明治七年) |
長谷寺境内に教立学舎(後の長谷学校/第一小学校の前身)が創設される。 |
| 1887年 (明治二十年) |
境内にあった五社明神社(神明、春日、白山、稲荷、天神を奉斎した長谷村の鎮守)を甘縄神明社へ合祀される。 |
| 1900年 (明治三十三年) |
別当の慈眼院が横浜市久保山に移転し光明寺と改称す。 |
| 1901年 (明治三十四年)頃 |
思想家・高山樗牛が長谷寺境内に居処す。 |
| 1909年 (明治四十二年) |
境内の大黒堂が建立される。 |
大正時代
| 年 | できごと |
| 1923年(大正十二年) | 関東大震災により罹災す。 |
昭和時代
| 年 | できごと |
| 1943年(昭和十八年) | 観音堂再建成る。日本各地の宝筐印塔(ほうきょういんとう)を刻んだ板碑が本堂基壇下から発見される。「1308年(徳治3年)」の刻銘あり。 |
| 1952年(昭和二十七年) | 聖観音像(通称「大麻観音」)と高浜虚子句碑が建つ。 |
| 1953年(昭和二十八年) | 大野伴睦(萬木)句碑が建つ。 |
| 1954年(昭和二十九年) | 単立宗教法人として正式に認可される。境内入口付近に久米正雄胸像が置かれる。 |
| 1959年(昭和三十四年) | 高山樗牛が長谷寺境内に住んだことを記録する碑が建立される(高山樗牛住居址碑) |
| 1972年(昭和四十七年) | 丈六 阿弥陀如来坐像の本格的な調査が実施され、修理が開始される。 |
| 1974年(昭和四十九年) | 上記、丈六 阿弥陀如来像の修理が完了す。 |
| 1980年(昭和五十五年) | 長谷寺宝物館がオープンす。 |
| 1983年(昭和五十八年) | 石造 釈迦如来坐像の開眼供養を厳修す。 |
| 1986年(昭和六十一年) | 昭和の大修理にて観音堂拝殿が再興され落慶法要が盛大に執行される。 |
平成時代
| 年 | できごと |
| 1991年(平成三年) | 本尊・十一面観音の大光背落成。 |
| 1992年(平成四年) | 慈照院本堂の再建が成る。 |
| 1996年(平成八年) | 大黒天像が宝物館へ遷座す。大黒堂が宝物館1階に併設される。 |
| 1998年(平成十年) | 丈六・阿弥陀如来の光背落慶供養が厳修される。 |
| 2003年(平成十五年) | 新地蔵堂落慶供養ならびに地蔵菩薩立像新添につき開眼供養を厳修す。 |
| 2005年(平成十七年) | 長谷寺復興に尽力した第31世・住持「善誉上人」を顕彰し、肖像を観音堂内に安置す。 |
| 2015年(平成二十七年)10月 | 観音ミュージアム がオープンする。梵鐘(重要文化財)、十一面観音懸仏(重要文化財)、観音三十三応現身像などが当館へ移され収蔵される。 |
長谷寺の歴史を簡単にまとめて説明
長谷寺は、正式名称を「海光山 慈照院 長谷寺」と言い、古くから坂東三十三観音霊場の第四番札所の指定を受ける古刹となる。
本尊は、通称「長谷観音」とも呼ばれる、像高9.1メートルもある寄木造りの十一面観音菩薩立像になる。
この仏像は721年(養老5年)、当時、大和(現・奈良県)は長谷の山中にて修行中だった徳道上人の発願により、2人の名もなき名工(仏師)が造立したもの。
この当時、長谷山中には十丈(1丈=3.03m)ほどの楠の大木が植っており、徳道上人はこの大木を見るたびに観音像を作りたいという思いを募らせていた、その矢先、2人の名もなき名工(仏師)が突如、現れた。
徳道上人の思いを汲んだ二人の名工は、程なくして観音像を作り上げ、1体どころか2体が瞬く間に完成した。
徳道上人は歓喜に沸き立ち、最初に完成した観音像を大和の長谷寺へ奉安、もう1体の観音像は縁深き地に現出して多くの衆生救済を願いながら海へ投じた。
そして736年(天平八年)6月18日の夜のこと、三浦郡長井浦に観音像は漂着することになり、当地の漁民により鎌倉の当地へ移された。
この後、この観音像の由緒を知った村人たちは徳道上人を招き、上人は当地に寺を建てたとされる。
‥‥以上の話は江戸時代以前より伝承される「長谷寺縁起」に拠るもの。
長谷寺に関する資料は鎌倉時代以降のものが多い
長谷寺に伝蔵される資料の数々は、鎌倉時代以降に記されたものが多く、もし奈良時代に創建されたのであれば、遅くとも13世紀半ばまでには現在の寺観が整えられたとみられている。
鎌倉幕府からも信仰が寄せられた
重要文化財指定を受ける梵鐘には「文永元年(1264年) 新長谷寺」の陰刻が見えることから、鎌倉時代にはすでに篤き尊崇が寄せられていた背景を物語る。
その他の例証としては、鎌倉幕府有力御家人の一人である大江広元(おおえのひろもと)は当寺を再建しているのだが、やはり鎌倉幕府からも一目置かれていたことになる。
歴代足利将軍の帰依を受け支えられた
1342年(康永元年)、足利尊氏が観音像に金箔塗りを施し、1392年(明徳三年)には足利義満が観音像の光背(こうはい/背中の輪っか♡)を制作した。
徳川家康公も信仰を寄せた
1607年(慶長十二年)には徳川家康公の発願によって再興される。
1677年(延宝五年)には、長谷寺住持の弁秋上人が尽力し、浄財二千両の寄進の受け、観音再興の大事業が成った。
長谷寺の宗派の変遷
長谷寺は奈良の長谷寺の流れをくんでいたものと推定されるが、奈良の長谷寺は東大寺の末寺だったことから、当初は華厳宗に属した寺院だった可能性も指摘される。
その後、奈良の長谷寺は、興福寺の末寺に置かれたことにより法相宗へと素敵に改宗。
16世紀以降になると中興の覚鑁上人(興教大師)の影響によって真言宗へと変わる。
そして江戸時代を迎えると徳川家康公の帰依を経て営まれた境内の大改修工事を機とし、家康公(松平家)が信仰を寄せていた浄土宗系の寺院となる。
戦後の宗教界の混乱期、長谷寺は浄土宗の組織から独立し、現在は浄土宗系の単立寺院として以前にも増して幅広い信仰が寄せられる。
